部下を持ったら押さえておきたい上手に指導・育成するポイント
職場でキャリア積んでいくと、部下や後輩を持つようになります。彼らをどのように指導すれば、本人と会社のためになるのか。いくつかのポイントを押さえておきましょう。
- 6,464views
- B!
部下の指導で気をつけるべき点とは
有能なビジネスパーソンは、次々に仕事をこなしていきます。そうしてキャリアを積んでいくと、部下や後輩を持つ機会も多くなるでしょう。彼らにどのような指導をすればいいのか、悩んではいませんか。もちろん彼らの性格によって臨機応変な対応は必要ですが、ある程度共通しておさえておきたいポイントもあるのです。今回は、そんなベーッシクな点をご紹介します。
まず初めに全体像を伝える
どんな仕事にも、ゴールがあります。そのゴールに向かってチームメンバーが役割分担をこなしていくのが、仕事の基本的な流れです。部下を指導するときは、まずこのゴールを伝えましょう。今から携わる案件はどういう内容で、何を目標としているのか。簡単にでもこれを伝えておくだけで、アナ阿多の指導に対する彼らの理解度は格段に上がります。
ゴールもわからずただ作業のやり方のみを教えるだけでは、彼らは何か起こった時に臨機応変に対応することができません。その結果、少しでもイレギュラーなことが起こるとその都度あなたや他の上司に対処法を仰ぐことになってしまいます。こうした手間を防ぐためにも、まずは全体像を教えるようにしましょう。
指示するのではなく本人を「導く」
部下に何かを指導するとき、新入社員でなければ1から10まで細かくあなたが指示する必要はありません。むしろ、それはあまり良くない方法でしょう。それは第一に、説明するのに要する時間が長くなってしまいます。第二に、やり方があまりに窮屈に決まっていると、実際に仕事を行う部下がやりにくさを感じます。ですから、全てを支持するのではなく、あくまで導くイメージで伝えるようにしてください。
あくまで、基本的なことや絶対に外せない点を伝えることに重点を置きましょう。右も左もわからない新入社員であれば丁寧に全て教える必要がありますが、ある程度経験のある部下なら自分なりのやり方というものを持っているものです。そのやり方を尊重した方が、部下自身が効率よく仕事を進められます。
部下の質問を促すテクニック
大抵の場合、新しい案件や作業について指導する際、一通りやり方を伝えた後に質問はあるかと聞くかと思います。この時「質問はあるか」とストレートに聞くのはいい方法ではありません。もっと部下が気軽に質問をできる言い方をした方が、結果的に彼らの理解が深まることになります。
テクニックとして、「念のため再確認したい点はあるか」という効き方をするという方法があります。こうすることで、部下が「この点についてもう一度聞きたいが、今説明してもらったことを聞くことはできない」と思っている点をクリアに出来ます。もちろん、こうして出てきた質問に対しては、快くもう一度教えましょう。わからないまま突っ走ってした失敗をしりぬぐいするよりも、事前に2回言う方がダメージはありません。
良い指導で良い部下を育てよう
いかがでしたでしょうか?ここで抑えた基本を守れば、あなたの手間が省けるうえに、部下自身の成長度合いが大きくなります。あなたも部下も、同じ会社の大切な財産です。そうして部下を指導できる能力がある人間こそ、本当の一流エリートであると言えるでしょう。
【昇進/転職祝い】上司から部下へ贈ると喜ばれるプレゼント5選
【昇進/転職祝い】部下から上司へ贈りたいプレゼント5選
この記事のキーワード
この記事のライター
美味しいものと食べることが好きすぎて、食品関係の仕事をするように。グルメ、イベント、ファッション、美容を中心に、映画や小説などのエンタメ記事を書いていきます。












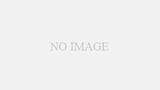
コメント